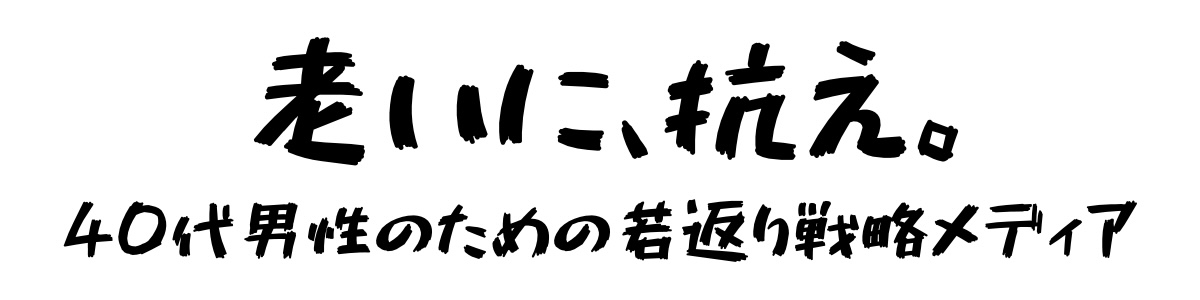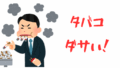※これはアンチエイジングの物語です。
酒がうまいと感じたのは、24歳の頃だった。
上司に連れて行かれた居酒屋で、生ビールを一気に流し込んだ瞬間、
喉がカーッと熱くなり、身体の奥まで電気が走ったような気がした。
「これが、大人の味か」
まだ社会人として右も左もわからなかったあの頃、
酒を飲める自分に、少しだけ誇らしさを感じた。
いつしか酒は、“日常の一部”になった。
仕事帰りの一杯が欠かせない。
家に帰れば缶ビールが冷えていて、風呂上がりにプシュッと開ける。
金曜の夜は飲み会、土曜の夜は家飲み、日曜の昼もつい缶チューハイを一本。
酔えば嫌なことも忘れられる。
笑える。しゃべれる。眠れる。
ストレスを酒で流すことが、いつしか「生きる術」になっていた。
でも、それは“錯覚”だった。
40歳を過ぎてから、体の異変に気づいた。
まず、朝がつらい。
寝起きがだるく、口の中がネバつく。
胃のあたりが重くて、何を食べてももたれる。
「年のせいかな」と思っていたが、ふとした血液検査で肝臓の数値が引っかかった。
「ちょっと飲み過ぎじゃないですか?」
そう言った医師の言葉が、胸に刺さる。
“自分は酒に強い”“大丈夫”と思っていたが、
体は確実に、悲鳴を上げていたのだ。
その日、初めてスマホで「アルコール 依存症 初期症状」と検索した。
すると、自分の行動があまりに当てはまりすぎていて、冷や汗が出た。
・毎日飲まないと落ち着かない
・飲む量が増えてきた
・やめようと思ってもやめられない
・肝臓の数値が悪い
・家族から心配されている
どれも当てはまっていた。
自分は、いつの間にか酒に縛られていた。
“飲まなければやってられない”という呪いにかかっていた。
飲んでいた時間は、何も生んでいなかった。
酒があったからうまくいった夜なんて、一度もなかった。
むしろ、酔って失言をしたり、翌日の仕事に響いたり。
翌朝の後悔ばかりが積み重なっていた。
「なんで、やめなかったんだろう」
そう思った瞬間、胸が締めつけられた。
10代の頃、父親のことが嫌いだった。
理由は、酒癖が悪かったからだ。
酔って怒鳴る。
酔って泣く。
酔って何も覚えていない。
母がどれだけ泣かされていたか、どれだけ家族が迷惑を被ったか。
「こんな大人にはなりたくない」と思っていたのに。
気がつけば、自分も同じような道を歩いていた。
妻は言った。
「あなた、昔より飲む量が増えたよね」
「なんか最近、酒飲んでる時しか楽しそうじゃないよ」
「子どもも心配してるよ」
娘が、風呂上がりの自分にそっと聞いてきた。
「パパ、お酒って、やめられないの?」
その一言に、何も言い返せなかった。
心のどこかで、「やめなきゃ」と思っていた。
でも、それはいつも「明日から」で、結局また今日も飲んでいた。
缶を開けて、「これで一日が終わる」と思っていた。
でも、本当はその一杯で「自分の若さ」が終わっていってたのだ。
飲まない夜は、最初はつらかった。
眠れない。イライラする。
でも、3日、1週間、10日と過ぎるうちに、
朝が軽くなった。胃の調子が戻ってきた。
そして何より、「酒がない夜が、こんなに静かで豊かだったとは」と気づいた。
今は、ノンアルの炭酸水を飲みながら、本を読んでいる。
子どもと話す時間が増えた。
家族の会話を、素面のまま覚えていられるようになった。
たったそれだけのことが、今の自分には尊くて仕方がない。
飲まなかったことで失ったものなんて、何もなかった。
でも、飲んでいたことで失っていたものは、数えきれなかった。
今なら言える。
酒をやめたからこそ、俺は“自分”を取り戻せた。
今もまだ、時々飲みたくなる瞬間はある。
ストレスがたまった日、悲しいことがあった日、うまくいかない日。
でも、そのたびに、あの日の娘の言葉を思い出す。
「パパ、お酒って、やめられないの?」
違う。
やめられる。
自分の意思さえあれば、人はいつからでも変われる。
もしも、この記事を読んでいるあなたが、
「そろそろやめた方がいいのかな」と思っているのなら。
今こそ、その一杯を、手放してほしい。
その一杯が、あなたの未来を奪うかもしれない。
でも、やめたその日から、未来は確実に変わっていく。
「酒に頼らない自分」に、もう一度出会ってみてください。
こちらもどうぞ↓