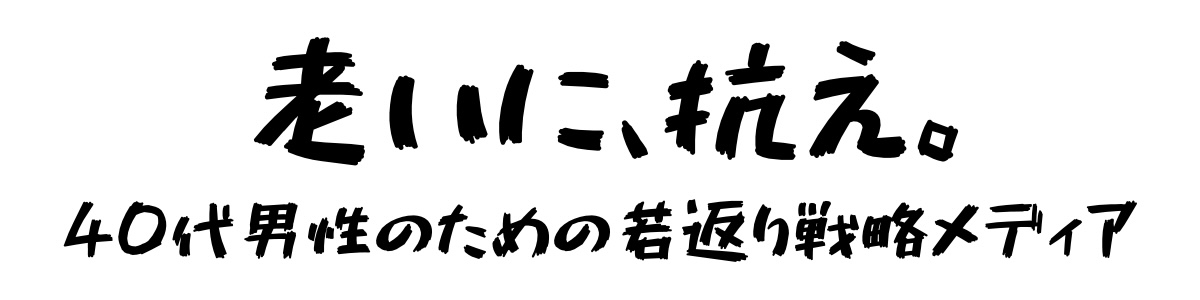※これはアンチエイジングの物語です。
大学1年の春、健太はタバコを吸った。
人生で初めて火をつけたその瞬間、自分が大人になったような気がした。
その煙の向こうに、自由とカッコよさと、ちょっとした背伸びがあった。
「タバコって苦くて不味いな」
最初の一口は、決してうまいものじゃなかった。
でも、横にいた友人がニヤッと笑って「慣れるよ」と言った。
その笑顔に引っ張られるように、健太は二口目を吸った。
何がキッカケだったのか。
思い返しても、たいした理由はなかった。
ただそこに、「タバコを吸う人」がいて、自分もそうなりたかっただけ。
ほんの、出来心だった。
それから二十数年。
40歳になった健太の肺は、悲鳴をあげていた。
職場の健康診断。
CT画像を見つめる医師の表情が、あからさまに曇った。
「うーん…健太さん、ちょっとこれは、肺に影があるね」
何気ないその一言が、彼の中で眠っていた後悔を目覚めさせた。
「…なんで、吸い始めたんだっけ」
忘れていたはずの、あの日の一本が、記憶の中にゆっくりと浮かび上がってくる。
楽しかった大学時代。仲間との夜。
コンビニ前で吸った煙。恋人と別れた夜に、ため息まじりの一服。
確かに、タバコはいつも傍にいた。
でも、あのときタバコがなくても、思い出はちゃんと色づいていたはずだ。
「うまいこと言ってさ…吸わせたの、あいつだったよな」
悔しさが込み上げる。
あのとき、誰かが「吸うなよ」って止めてくれていたら。
あのとき、自分にもう少しだけ勇気があれば。
タバコの煙のように、後悔はいつまでも消えてくれない。
健太は長年、タバコと一緒に歩いてきた。
1日1箱。月に30箱。年間360箱。
20年間で7,200箱。14万4,000本。
――吸いすぎだ。
そう思って、ゾッとした。
「体に悪いってわかってたのに」
「いつかやめようって思ってたのに」
「子どもが生まれたときも、禁煙できなかったくせに」
健太には、中学生になる娘がいる。
ふと気づけば、娘がタバコを嫌うようになっていた。
「パパ、くさい」
「なんでやめないの?」
その言葉を、笑ってごまかしていた自分が情けない。
「パパ、早く死んじゃうよ?」
何気ない一言が、心の奥まで突き刺さった。
健太は決めた。
病院を出たその日、ポケットにあったタバコを全部捨てた。
ジッポライターもゴミ箱へ。
喫煙所での談笑も、思い出に変えた。
禁煙は、簡単ではなかった。
手は震えるし、イライラするし、頭も重い。
けれど、そのたびに思い出すのは――娘の言葉だった。
「パパ、長生きしてね」
やめてみて、初めて気づいたことがあった。
「吸わない時間」が、こんなに静かで穏やかだったとは。
「吸わない自分」が、こんなに清々しくいられるとは。
今、健太は週末の朝にジョギングをしている。
息が切れなくなってきた。
階段を登るのも楽になった。
朝、鏡の前で「あれ、少し顔色がいいな」と思うようになった。
禁煙して1年。
もう、吸いたいとは思わない。
でも、完全に忘れることはない。
あの日の一本が、自分を作った。
そのことを忘れないために、健太は今も「後悔」という言葉を胸に刻んでいる。
そして、もしも。
もしもこの記事を、まだ吸っている誰かが読んでいるのなら――。
伝えたいことがひとつある。
「今すぐにでもやめろ」とは言わない。
でも、“なぜ吸っているのか”は、一度問い直してみてほしい。
カッコよくなりたい?
ストレス発散?
なんとなくやめられない?
どれも、20年後のあなたを守ってはくれない。
吸わない人生は、想像以上に軽くて自由だ。
肺も、心も、家族との時間も、全部がきれいな空気に包まれる。
その一歩を、どうか、今日のあなたが踏み出せますように。
こちらもどうぞ↓